宅建業法は権利関係、法令上の制限、税・その他の中でも最も得点源となる科目です。なので宅建試験を合格するなら「満点を取ろう」とよく言われると思います。
ここではなぜ宅建業法を満点にする必要があるのか。また、宅建業法を解くコツなどを私の体験談をもとに説明します。
あくまで体験談なので参考程度に読んでいただければと思います!
目次
なぜ宅建業法は満点を取ろうといわれるのか
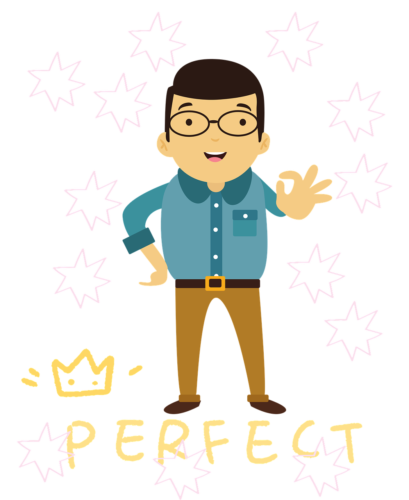
経験談から言わせててもらいます。
結論から言いますと、他の科目に比べて簡単だからです。
何がどう簡単なのか?と思いますよね。
つまり、テキストに書いてある内容をよく覚えていれば
問題を見た時に「テキスト通りにそのまま載ってる!」と思えるからです。
こう思えるから「簡単だ」となるのです。
「テキスト通りにそのまま載ってる!」と言葉通りに受け取ってもらうというよりも、感覚的に言うと「なんか,すんなり解ける」という感じですかね。
頭がしっかり冴えた状態でテキストの内容が理解できれば、宅建業法は得点源に繋がります。
裏を返せば、
テキストに書いてある内容が理解できない=宅建業法の点数は取れない
となり、宅建試験を落とすことにつながります。
あと、個人的にはひねくれた問題が少ないようなので頭を抱える必要はないように感じました。
宅建業法を解くコツ

テキストの内容は一字一句覚える必要はありません。書いてあることをほぼ理解し、1回目のある年の過去問を解いてわからなかった問題があればテキストに戻る。
そしてその年にわからなかった過去問の部分をもう一度解く。
解けたら、2回目に他の年の過去問を解く、その2回目の年の過去問でわからなければ、テキストに戻る。
の反復で「宅建業法の問題は簡単だ」と感じるようになるはずです。
宅建業法が満点を取ろうといわれるのは個人的にこのためのような為であるから、と感じます。
宅建業法が難しいなと感じた部分

得点源分野である宅建業法ですが、強いて難しいなと感じた部分があるのであれば
①報酬額の制限の計算問題
ですかね。
①報酬額に関しては計算が苦手ではないですが、なぜこれが「苦手」と思うのか考えてみました。
それは「問題のほとんどが文章問題であり、それで頭が慣れているのに、突然、問題で計算しろというのは脳の切り替えが必要」
となるからだと考えます。
だからもともと計算が苦手でなくても抵抗を感じてしまうのです。
これの対策として問題をどんどん解いて慣れるのが一番の近道だとは思います。それと計算が出て来たときは冷静になることですね。
②35条、37条の暗記 に関しては少し多めな暗記があるということで苦手意識が出てくるのでは、と思います。
宅建業法はあまりひねくれていないのでこの科目は早いうちにほぼ理解できる状態にもっていった方がいいと思いますね。
そうすれば、早く覚えた分、権利関係といった出題範囲の広い分野にすぐ取り掛かることができるので。
権利関係は宅建業法より結構奥が深く民法の判例などもやっかいなので宅建を初めて受ける方で独学でやっていこうと思う人は勉強の仕方を考えた方が良さそうです。
勉強の仕方など自身が持てそうにない方は通信講座で講師などの有資格者からサポートを受けるのが良いと考えます。
勉強の方法や民法の判例問題などを教えてくれる相談や講座をアガルート通信講座から出ています。
講座をうまく活用して4科目を乗り越えられるようにしてはいかがでしょうか?

