「簿記」という資格を知っている方の中には日商簿記と全商簿記の違いは何なのか?疑問を持っている方もいます。今回は日商簿記と全商簿記の違いについて解説していきます。
目次
・全商簿記について
まず、全商簿記とは何なのか?
インターネットで全商簿記と検索すると以下のようなサイトがトップに出てきます。
(公益財団法人全国商業高等学校協会HPより)

左上に「公益社団法人全国商業高等学校協会」と書いてあります。
この名前から分かる通り高校で習う簿記の範囲から出題される資格試験となっています。
また、よく「全商簿記」と言われますが正しくは
簿記実務検定試験
と呼びます。
この簿記実務検定試験には
1級 2級 3級
の3つのランクに分かれています。
難易度は1級>2級>3級の順となっています。
3級はよく見かける八百屋や金物屋などの個人経営を経営しているところで役に立つレベルです。
ドラえもんに出てくるジャイアンの母ちゃんが営んでいるところは個人経営なので3級が役立ちそうですね
2級は個人経営してる店ではなく規模の大きい(株式会社○○とつくところ)会社で2級の知識が活かせます。
そして1級は2級と同様、株式会社で役立ちますが、2級よりも奥が深く、会計に関する法律や製品の製造に関する原価(金額)の計算の知識が身につきます。
1級は3級と2級と違い、「会計」と「原価計算」の2分野を勉強しなければなりません。
試験は毎年1月と6月の2回実施されています。
もっと詳しく知りたい方は下記の公式HPでご確認ください。
↓
日商簿記について
次に日商簿記についてインターネットで調べてみるとこのような公式サイトが出てきます。
(日本商工会議所・各地商工会議所HPより)
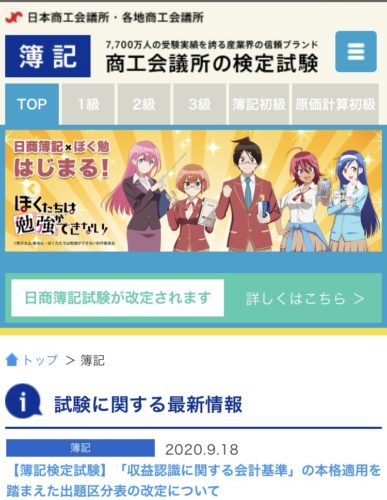
このサイトでは左上に「日本商工会議所・各地商工会議所」と書いてあります。
日本商工会議所は日本の経済団体の組織であり、上記で述べた公益社団法人全国商業高等学校協会よりも規模が大きい団体となっています。
日商業簿記の正式名称は
日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験
と言います。
この資格試験も級があり、
1級 2級 3級 簿記初級 原価計算初級
の5つのランクに分かれています。
難易度は全商簿記と同様に
1級>2級>3級>簿記初級・原価計算初級の順となっています。
3級から受ける方が多いので3級以降を説明しますと
3級は商業簿記という企業の経理の基礎を学ぶことができます。また、これに合格することによって青色申告の手続きの知識が身につきます。
1級では商業簿記や工業簿記の他に原価計算や会計学等が加わり、さらに難易度が高くなります。
試験は毎年2月と6月と11月の3回実施されています。
日商簿記についてもっと詳しく知りたい方は下記の公式HPからご確認ください。
↓
就職や転職するといった場合は2級以上持っておくと良いでしょう。
日商簿記と全商簿記の違い
全商簿記と日商簿記とでは求められる知識の幅が違います。
全商簿記は
「公益社団法人全国商業高等学校協会」というだけあって高校生のレベルに合わせた資格となっています。
一方で日商簿記は
会社で使われるような実践に近く、全商簿記と比べてレベルも上がり、より深い知識が求められる資格です。
日商簿記と全商簿記どっちをとるべきか
全商簿記でも日商簿記でも簿記に関して学べることは間違いありません。
しかし、これから就職や転職で会社に入り、お金の流れや材料の仕入れから販売の仕方をしっかり学びたいと考えている方は日商簿記の勉強をオススメします。
しかし、そこまでではなく多少、簿記の知識をつけておこうと考えている方であれば全商簿記を勉強をオススメします。
また、日商簿記に関する記事を下記の記事でも解説していますのでこちらもご覧ください。
↓
まとめ
全商簿記とは
公益社団法人全国商業高等学校協会が主催する簿記実務検定試験のことであり、3〜1級までの資格がある。
日商簿記とは
日本商工会議所及び各地商工会議所が主催する日本商工会議所及び各地商工会議所主催簿記検定試験のことであり、3〜1級までの資格がある。
全商簿記と日商簿記の違いは
求められる知識の幅が違う
以上、日商簿記と全商簿記の違いについて解説を終わります。